 |
「フレッシュ・フライ・ワイルド&ボールド」
コールド・クラッシュ・ブラザーズ
「ヒップ」という、あるフィーリングを現す言葉がある。大好きな言葉だ。元々は昔のジャズマンが使った古い言い回しで、端的に言えば「イカしてる」というような意味なのだが、ニュアンスとしてはもっと微妙なものを含んでいる。ジャズの大御所セロニアス・モンクに「ugly
beauty」という曲がある。ダサいけれどかっこいい、一見醜いけれど素晴らしい、というような意味のタイトル。どういうことかと言うと、例えばいかにも格調高いものや、高級品などは素晴らしいに決まっている。そんな既に評価の固まったものを讃えても当たり前すぎてつまらない。むしろ誰もがダサい、安物くさいと馬鹿にするようなものの中に芽吹くかっこいい要素を見つけ出し、新たなるものとして提示するというのが「ヒップ」というフィーリングなんだ。応用として例を挙げると、誰かがいい腕時計をしていたとする。「ええ時計してまんなあ、どこのブランド?」「無名ですわ」「しかし高そうやのう、なんぼしましたん?」「ああ、ホームセンターで580円で買ったんですわ。で、バンドだけ換えましてん」「うそー、めちゃかっこええ、おれも真似しよ」・・・・。と、このようなノリがヒップってやつなんだ。つまり「なーんでこんなものが?」という固定観念をはぐらかし、逆に「イカしてる」と価値転換させ、むしろうらやましがられるようなものに代えてしまう、ちょっとした創造性のことを言う。キーワードは「ハンドメイド」。なお「チープシック」ってやつにも似ているけれど、そこにもっと下世話かつ破格の風が吹くのが「ヒップ」なんだ。で、前置きが長くなったけれど、ヒップホップだ。衰退していったジャズが持っていた「ヒップ」の精神を前面に押し出し、ゼニはないけれど余りある発想力で、道端に転がっているガラクタのようなものを素材として、面白いものを作り出すノリ。そこからヒップホップは始まった。1970年代後半から80年代前半にかけて、スラムでくすぶっていた連中の手によりラップやブレイクダンスやグラフィティアートが生み出され、やがて全世界に広がるポップカルチャーにまで成長していき、今に到っている。そんなヒップホップ創世記を支えた伝説的代表格がこのコールド・クラッシュ・ブラザーズなんだよ。これを聴くと、今の洗練されたヒップホップに比べて単純だな、と思えてくるかもしれないが、それを越えて余りある創始者独特の「気」、そう、「ヒップさ」のみなぎった気を感じることができる。

|
 |
「ラブ ア ダブ スタイル」 パパ・ミシガン&ジェネラル・スマイリー
ヒップホップはレゲエの弟である。まず、ジャマイカ・キングストンのスラムでくすぶっていた貧乏な音楽好きの若者たちが、楽器を買うこともできず、DJがかけるレゲエに合わせて歌ったり踊ったりしていた。それがやがて「ダブ」というスタイルの新しい音楽を生み出した。1970年代半ば頃のこと。同じ頃、ジャマイカからニューヨークの貧民街・サウスブロンクスに移民したクールハックという男がいた。彼はそこでジャマイカンレゲエ(ダブ)のサウンドシステムを持ち込み、ブレイクビートという手法を編み出し、そこからヒップホップが始まった。ブレイクビートとは、他のレコードのおいしい部分を切り貼りして全く別の新しい音楽に作り変えてしまうワザのことで、「ダブ」も同じ手法を取る。レゲエのリズムをそのまま採用し、より音響加工を施すのがダブで、一方ファンクのリズムを採用し、グルーヴ性を強調するのがヒップホップ。どちらもやはり「ヒップなフィーリング」がキーワードなのだが、79年発表のミシガン&スマイリーのこのアルバムは、ダブレゲエの持つヒップさがよく出ている。音もいいが、このアルバムの裏ジャケットもまた象徴的だ。2人の全身写真が載っているのだが、ファッションが凄いのだ。安物のジャージ上下、小悪党風のグラデーションのグラサン、ハット、首にはスカーフを巻き、足元をよく見るとソックスにジャージのすそを入れ、何と革靴を履いている。なんでそんな格好をしているのか、答えは簡単だ。「貧乏なのでそれしか服を持っていない」から。持っている唯一の服「ジャージ上下」で精一杯お洒落をすると、そうなりましたというわけ。ダブやヒップホップの創始者とはみんな同じようなもので、やがてそれを「かっこいい」と真似をした奴らが、流行のファッションにしていった。こいつらこそが、今日び街を歩いている若者のストリートファッションの原点、創始者なんだ。「ないのなら、ありあわせで作ってみようやホトトギス」・・・・、ダブやヒップホップの、固定観念をはぐらかしてくれる面白さを突き詰めていくと、必ずここにたどり着く。いわば「ジャージに革靴」というような足元から全てが始まったんだ。そしてぼくがこういうノリが好きなのは、日本のシーカヤッキングというもの自体が今、創生期なのであり、他人様の固定観念を外してナンボというところがあるからなんだ。ちなみにうちの「アイランドストリーム」という屋号は、「日本シーカヤッキングの創生期」という意味で付けている。日本神話の最初は、潮汐流が島々を生んでいく自然観から始まるからね。その精神は「ジャージに革靴」的なノリにこそ通じている。

|
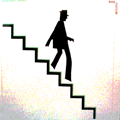 |
「ベース カルチャー」 リントン・クウェシ・ジョンソン
ジャマイカからのイギリス移民、リントン・クウェシ・ジョンソンはダブ・ポエットの代表的存在だ。ダブ・ポエットとは文字通り、上にあげたような「ダブ」のリズムトラックをバックに、純然たる「詩」を詠むというスタイルの詩人である。ヒップホップやダブってジャンルは、まさになんでもありなのだ。この人は、普通の詩人としても十分通用する力を持っている。日常の茶飯事から恋愛ごとに到るまで、あらゆるものに政治性を絡めるというのが彼の特徴。そういうものは平和ボケの日本では徹底的に嫌がられ、流行らないスタイルなのだが、彼の出自ではそれがごく自然なのである。「高い政治性」を通底させることにより、人種や国籍を超えてアピールする表現となっているのだ。バックトラッックのダブを手がけるのは、このHPの別の所でも触れている鬼才デニス・ボーヴェルで、太々しい幻惑的原色感とも言うべきフィーリングとの相性も面白い。で、ぼくはこれを聴きながら、「シーカヤッキング・ダブ・ポエット」てな手法も面白いかもしれないなと思ったのだった。海を詠む、自然を詠むと言っても今更、万葉集やら松尾芭蕉どうこういうのもピンとこないからね。

|
 |
「Heroes of Reggae Dub」 The Skatalites & King Tubby
レゲエの前身は「スカ」という2ビートの楽天的かつ海の香りのする音楽。その代表格がスカタライツだ。トランペット、サックス、トロンボーンといったホーンセクションを前面に押し出し、かなりジャズ色の強い音を出すバンドだ。モダンジャズ的な高度なやつではなく、デキシーランドジャズ的な娯楽性の強い音。おそらくジャマイカのラジオに侵入してくるニューオリンズの音楽番組からの影響を受けているのだろう。音の隙間が多く、その崩れた感覚がなんともダサかっこいいスカタライツ。で、その彼らの音源を、ダブ界の大御所キングタビーが、過激に音処理を施したのがこのアルバム。濃い。むせかえるほどのけだるい濃さが、めちゃくちゃ熱苦しい熱帯夜の海辺などで、はまった。

|
 |
「King Tubby Special 1973-76」
King
Tubby & The Observer All Stars
で、そのキングタビーの最初期の作品集。ダブの最も原初的なエッセンスが真空パックされている。ただ聴いて楽しむだけならば、新しい音源の方が聴きやすいというのがこの手のやつの相場なのだが、こういう創生期ものって、荒々しいひらめき、気合、やろうとしていることの熱っぽさなどが節々にほとばしっていて、それが「ハンドメイド感覚」に貫かれていて「おや」っと思わせられる。そこが面白い。キングタビーのダブは、重さ、濃さ、幻惑感の中に原色が飛び散るかのような色彩感の鮮やかさがあって、凄いのだ。

|