 |
「キープ ライト」 KRS ONE この人は本当に素晴らしい。1965年NYのブルックリン生まれ。生後すぐ、世界に悪名轟かせるスラム街・サウスブロンクスに引っ越す。7歳の頃、伝説的ヒップホップ創始者クールハークのブロックパーティに触発され詩を書き始める。高校を中退し、家出。大麻売買で逮捕され獄中生活を送る。出所後、ホームレス施設に入る傍ら図書館に通い猛勉強、インテリジェンスを磨く。グラフィティアートを教えてくれた友人の提案でKRS−ONEと改名(Knowledge Reighs Supreme Over Nearly Everyone)。そこからラップアーティストとしてのキャリアをスタート。80年代半ばのこと。ブギーダウンプロダクションズなど人気グループで活動すると同時に、様々な大学で「非暴力主義」を唱える講演活動なども行う。そうしてヒップホップ創生期から黄金時代を走り抜けてきて、未だにトップアーティストとしてのレベルをキープしつつ、テンプル・オブ・ヒップホップという機関を設立し、「世界カルチャー」としてのヒップホップの価値を啓蒙する。2001年には国連で「ヒップホップカルチャー宣言」をし、今では講演活動から、子供たちのヒップホップ体験学習やセミナーまでを手がけている。言わばヒップホップ伝導師といったところか。この人のインタビューのアメリカ批判、ブッシュ大統領批判は非常に的確で、かなり見るべきものがある。そしてこう言う「オレは黒人だという意識すらない。肌の色うんぬん言う前に、オレはヒップホップという国の住人だ。ヒップホップは民族や国境という壁を越えて、世界の多様性を謳歌するためにあるカルチャーだ。実際に全世界の若い連中が創造性をヒップホップに傾けている。その平和的精神こそがテンプル・オブ・ヒップホップだ」・・・・。さてこの2004年発売の最新作だが、まず非常に音が太い。ギャングとか麻薬とか売春とかをかっこよく言う巷の流行ヒップホップの影響を受ける若い連中に対し、「まともな道を歩め」と、やたらと野太い声で、硬質のヘヴィな音で、熱い血潮で、説教する。少々自慢気なタッチなのだが、それがまたヒップホップ特有の味となっていて面白い。まだまだ血気盛んなのだ。で、思うのだがこういう人がもしシーカヤックをやるとしたらさらに面白い。黒人が「アウトドア」を楽しむという文化がないのもまた、おかしなことだからだ(それはアイスTというラッパーも「おれの色は死だ」という著書で言っている)。なおテンプル・オブ・ヒップホップのHPはここをクリック。 |
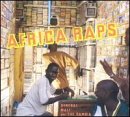 |
「アフリカ ラップ」 VA アフリカには今、全域に渡ってヒップホップをやる若者が大勢いるらしい。アメリカに奴隷として連れていかれた人々が、ブルース、ジャズといった音楽を生み出し、その集大成みたいなのがヒップホップとなった。そして、長い旅路の末にようやく里帰りした、といったところか。いずれにせよアフリカ起源のものだから、アフリカ人がやったって全くおかしなところはない。で、このアルバムは西アフリカのセネガル、マリ、ガンビアの三国の人気グループの曲を集めたオムニバス盤だ。特にセネガルはヒップホップ大国で現在6000ものグループがあるという。10年ほど前の初期のやつはアメリカの「ギャングスタ・ラップ」という暴力的なラップの物まねが多く、イスラム教徒が多いセネガル人には受け入れられなかったが、「ポジティヴ・ブラック・ソウル」というグループが出てきて、様相を一変させた。セネガルの「ムバラ」というポピュラー音楽と融合させ、土着の「ウォロフ語」でラップするというスタイルを完成させたのだった。セネガルのラッパーは90%がイスラム教徒で、その歌詞はけっこう政治的、倫理的な要素が強いのが特徴。例えば前述した「ポジティヴ・ブラック・ソウル」の最初のヒット曲は「他人の言うことに振り回されるな、正しい答えは己の思考の中にある」という凄いタイトルだ。ちなみに「リトル・パリ」と呼ばれる首都ダカールを持つセネガルの人口の80%は30歳未満らしいが、そういう若い奴らへのメッセージとして機能しているのだろう。なおDAALA Jという連中は去年イギリスの音楽祭で大賞を取って、セネガルラップを世界に広めるきっかけとなった。そしてガンビア。「第二のジャマイカ」とも言われ、レゲエの要素を取り入れたヒップホップが多い。ガンビアはセネガルの首都・ダカールからバスで5時間という距離なので、セネガルのTV放送とも合わせて、結構影響があるようだ。そこにレゲエの要素をまぶす。そして同じくダカールから電車で2,3日という距離のマリ(首都・バマコ)。マリのポピュラー音楽は、グリオ(宮廷音楽家)ミュージックあるいは、wassoullouミュージックと呼ばれるもので、ラッパーは少ないようだ。そしてビートが難解で、おまけに歌詞も、例え英語で歌われていたとしても理解しずらいものだという。・・・・・・と、このようなことがライナーノーツに事細かに書かれている。ドイツのレーベルからの発売らしく、ドイツ語と英語の両方が記されている。これ読むだけでもかなり勉強になるよ。で、音なんだけど、このCD実にいい。アフリカ色がよく出ている。アメリカのものに酷似しているものも多いが、なんというか空気が違う。アメリカのラップはドメスティックというか、自国に閉ざされているような感じのものが多いが、アフリカのラップは風がよく通っている。世界に繋がる風。ちなみにこれら全てのオリジナル盤は、CDではなく、カセットテープなんだよ。このアルバムジャケットを良く見ると、山積みになったカセットだ。ところでアフリカのラップシーンについて興味ある人は、ここをクリック。そしてセネガルのラップシーンに興味ある人は、ここをクリック。 |
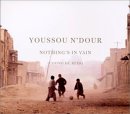 |
「NOTHING IN VAIN」 ユッスー・ンドゥール アフリカのミュージシャンで最も世界的に有名なのがセネガル出身のこのユッスー・ンドゥールだ。1959年にグリオ(宮廷音楽家)の家柄に生まれ、フランスに留学。伝統音楽「ムバラ」をベースにして、ロック、レゲエ、ファンクなどといったグローバルグルーヴを取り入れることによって、アフリカという枠を超え、全世界にアピールするポップ性を獲得することに成功した。言わば第一人者である。この人はまず声がいい。スケールの大きな、アフリカの自然そのものが育んだような、暖かで深い声を持っている。やや鼻にかかった、アメリカ黒人の「ソウル」とはまた違った、大らかな高揚感を誘い出すソウルフルな声。アフリカ人としての「誇り」「エナジー」をポジティブに描き出すために天から与えられたような声だ。この声がある限り、どんなに洋風の音になっても、水で薄めたようにはならないんだよ。で、このアルバムは、アコースティックな音作りで渋いのだが、楽曲が素晴らしく、よって彼の声の素晴らしさが輪郭鮮やかに躍動している。 |
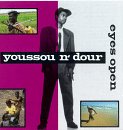 |
「アイズ・オープン」 ユッスー・ンドゥール セネガルのウォロフ語でXIPPI(ヒッピー)とは、「より開かれた目」という意味らしい。このアルバムは映画監督・スパイクリーが主宰するレーベルから出されたもので、ユッスー・ンドゥールが本格的にワールドワイドを意識して作った作品。「より開かれた目」というタイトルは、その意思表示と言ったところか。どの曲も大陸的な広がり感があって、気持ちいい。そしてやはり声が素晴らしい。ものすごく人間的なんだけど、単純な「喜怒哀楽」を超えた、もっと野性的というか、生物的な声なんだよ。これはシーカヤッキングやトレッキングの行き帰りなんかに聴くと凄くハマるアルバム。特に3曲目の「no more」は、アコースティックギターと熱唱とのバランスが素晴らしい。で、歌詞なんだけど全曲、倫理観が非常に強い。・・・・「世界人類はみな兄弟だ」「みんなそれぞれ可能性を持っている。その可能性を分かち合おう」「融合することはパワーだ」「異文化に敬意を払おう」「社会意識を持って意見を交換しあおう」・・・・・というようなことについて歌っている。「ケッ」と思うかもしれないが、実はアフリカの詩というのは多く「倫理」について謳うものが多い。アフリカの伝統として、生活とアートは分かちがたく繋がっている。だからアート性だけを抽出し純粋培養したものなんてない。現実生活をよりよいものにするためにアートがあるのであって、ましてや詩は自分たちの生活の「主権性」のためにある。言わば「個人性が運命をリードするということを自覚するために詩を詠む」という考え方だから、そうなるのだ。それはセネガルのノーベル賞詩人、レオポルド・セダル・サンゴールもそうだし、またなぜかアメリカインディアンの詩も同じなのだが、「最高の詩情は最高の倫理である」というところを、この人間的かつ野性的な声が情感深く歌い上げる。 |
 |
「ムラートス」 オマール・ソーサ キューバ出身、スペイン在住のピアニスト、オマール・ソーサ。人種や民族といった壁、境界線を自らのピアノが持つ力「詩情、ポエジー」でいったん解体し、そこから異文化要素を融合させるという、マジシャンのような芸術家だ。何がどう融合しているのか一目では見えない、つまり非常に自然な形で、しかも独創的な音楽になりきっているのである。こんな天才そうそういない。彼の態度は基本的に「汎アフリカ二スト」のスタンスで、全世界に飛び散ったアフリカ的要素を、ひとつにまとめあげるという、言わば素晴らしい料理人なんだ。で、それに最も成功したのは前作の「センティール」というアルバムで、モロッコの「グナワ」というトランス音楽の触発から出来上がったものにほかならないのだが、今作ではそれに飽き足らず、インド音楽やクラシック(ドビュッシーからサティに到る流れが強いと言われる)の要素を織り合わせていき、エレガントさに一層の拍車がかかった。前作の成功でいい感じに肩の力が抜けたのか、このアルバムのリズムの揺らぎと重力感、本当に心地よい。・・・・・で、ぼくは彼のライヴ演奏をどこか渋い「お寺」で聴きたくなった。こういうハイブラウで深い表現は、お寺にこそよく合う(ちなみにお寺に最も合わないのは「墓」だ)。お寺というものの歴史的流れからすると、21世紀の寺は、最高に良質の芸能・アートの媒介によって、お互いかけ離れた人々を結ぶエレガントな場所とならなければならない、そうじゃなければ存在価値はない、と、ぼくは確信を持って思っている。そんな、お寺という「額縁」に最も似合う「絵」が、オマール・ソーサのこのような作品だ。この作品に寄せた彼の言葉を記しておこう。「文化の出会い、民族と伝統の交差点、そして融合、きみ、ぼく、かれ、かのじょ、そして全てのわれわれ、リズムの祝祭、音と色と一緒に、ムラートス(混血)!」。 |